-
【表彰伝達】
- 受賞名:
- 令和2年度岐阜県スポーツ賞
- 受賞名:
- 地域ボランティアスタッフ(CVS)特別表彰 岐阜市教育委員会
自転車競技部 尾方 裕仁
浅井 夢叶




確かな学力・技術、ものづくりを通した人づくり、部活動を通した人づくり
浅井 夢叶


令和3年度前期生徒会執行部の認証式が校長室で行われ、新生徒会役員8名一人ひとりに校長先生より認証書が手渡されました。昨年度に引き続き、生徒会長の新名君より『コロナ禍で今後の見通しが立たないが、学校全体を盛り上げるために頑張っていきたい』と抱負が語られました。


本校吹奏楽部が先日第24回定期演奏会を実施いたしました。当日は入場制限をかけさせていただいた中、約60名の方にご来場いただき、1年生にとっては始めて音楽ホールのステージでの聴衆を前にした演奏となりました。
また本年度卒業した3年生にとって最後の舞台ともなり、演奏会の最後にはサプライズの演出と演奏もいたしました。
当日の様子は以下のURLまたはQRコードより、YouTubeで確認できます。ぜひご覧ください。
来年度、令和4年1月15日(土)、サラマンカホールにて節目となる第25回定期演奏会の開催を予定しています!! 例年実施している工業展示も予定しています。皆様と再びホールでお会いできることを楽しみにしています!
URL https://youtube.com/watch?v=LAVpVkKoJB0&feature=share
↓ YouTubeアクセスQRコード
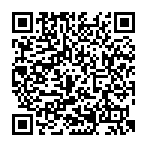



一次選抜試験の合格発表が9時に行われ、221名の合格者の発表がありました。受検生は自分の受検番号を見つけると家族や友人と喜びを分かち合い、写真を撮りあっていました。
今まで支えてきてくれた家族や友人へ感謝するとともに、次の新しい目標に向かって頑張ってくれることを期待しています。合格おめでとうございます。



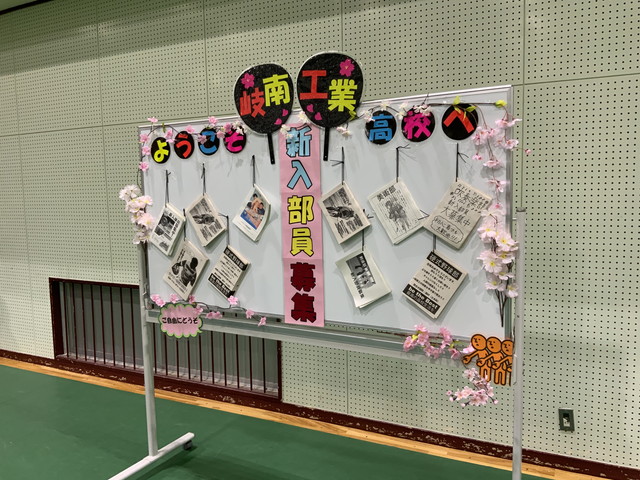
本校吹奏楽部が第24回定期演奏会を開催いたします。本年度は新型コロナウィルス感染拡大防止による入場制限のため、以下の日時にYouTubeによるLive配信を実施いたします。
YouTubeにアーカイブが作成され、後日でも視聴可能です。
URL https://youtube.com/watch?v=LAVpVkKoJB0&feature=share

生徒会では、卒業する3年生の先輩方への感謝の気持ちを込めて、プレゼントを用意しました。2月26日の予行練習の最後にはVTRの上映を、3月1日の卒業式の際には、体育館から本館へつながる通路に卒業記念の飾り付けをしました。VTR上映では、岐南工での3年間を思い出しながら視聴し、笑顔で語り合う姿も見られました。飾り付けは卒業を祝うメッセージと共に3年生の担任の先生の似顔絵を制作しました。卒業式後にはそこでたくさんの3年生が記念撮影をする姿も見られました。先輩方のご活躍を、在校生一同応援しています。3年間、お疲れ様でした!






卒業生267名が卒業式に臨みました。今年は新型コロナウィルスの感染拡大防止のため出席できる保護者も生徒一人に対し一人、国歌や校歌についてもCDによる演奏のみとし、出席者は歌わないなどの措置をとりました。
式では堀修校長が各学科代表生徒に卒業証書を手渡し、「新型コロナウィルスの蔓延によりあらゆる場面で変革を余儀なくされた1年であったが、岐南工で身につけた想像力と思考力で乗り切ってください」と激励。卒業生代表の土木科三上翔也君は「今まで当たり前だったことができない毎日で、その厳しい中でも立派な社会人となるよう準備をしてきました。私たちを温かく見守り支えてくださった方への恩を忘れず、これから社会で活躍できるよう頑張ります。」と答辞を述べました。




機械研究会の「第23回高校生新聞社賞」と生徒会執行部の「NPO法人 ぎふ・コートジボワールへの体育館シューズ寄贈」の表彰伝達式、陸上競技部の「2021日本室内陸上競技大阪大会」出場を激励する壮行会を行いました。
《生徒会執行部》
【壮行会】
《陸上競技部》
陸上競技部には校長先生と生徒会長からの激励の言葉と、同窓会長より同窓会からの激励金が贈られました。


3月1日に卒業される267名が出席し、表彰式と予行練習が行われました。新型コロナウィルスの感染拡大防止のため在校生は参加せず、卒業生と職員のみでの予行となりました。表彰式では3年間の学習に対する表彰や数多くの資格試験を取得したことに対する表彰、3ヶ年皆勤賞など15種類の表彰がされました。その後、同窓会入会式と卒業記念品贈呈式が行われ、最後に同窓会長の藤根様よりはなむけの言葉をいただきました。卒業は友人や母校との別れとなりますが、同窓会という新たな出会いの場でもあります。今後は先輩の同窓会員の方と一緒に見守り、ご支援をよろしくお願いします。




生徒会執行部が行っている“ecoプロジェクト”の一環で、3年生が使用していた体育館シューズ約230足をNPO法人 ぎふ・コートジボワールを通して寄贈しました。生徒会長がコートジボワールの民族衣装を着て、感謝状を受け取りました。


