マスク作りと寄付活動
地域活性化プログラム相談会
令和2年度 生徒総会
命を守る訓練
6月18日(木)のLHRで、「命を守る訓練」を実施しました。環境・防災委員やLHR運営委員の生徒が司会進行をし、最初に「減災力テスト」を行いました。次に、平成30年西日本豪雨災害についてのDVDを視聴後、各自の実体験を話し合い、今後予想される災害や指定避難場所等の確認等を行いました。「災害から自身の身を守るには、自ら行動し、情報を集め対策することが大切だと分かりました」「私達高校生も、自分の身は自分で守り、かつ誰かのために動けるように自覚をもって行動していきたい」などの感想が寄せられました。放課後には「帰宅確認メール」の配信及び返信の訓練を行いました。
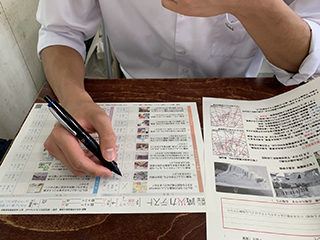 |
 |
 |
 |
行事紹介、白線授与式、部紹介
学校再開に向けての連絡(5月25日)
(1)6月学校再開後の生活について(学校長より) (PDF) 
(2)学校再開後の新型コロナウィルス感染症対策について(生徒用) (PDF) 
日々の生活で注意すべきことを時系列で挙げています。
5月28・29日の登校日の登校についてもこの注意事項に準じてください。
(3)5月28・29日の登校日について(PDF) 
○5月25~29日のオンライン学習支援講座及び登校日の時間割はこちら
(4)6月の分散登校について(PDF) 
生徒・保護者の皆様へ
オンライン回線の増設に伴う家庭学習支援の変更について
5月12日(火)以降、斐太高校のオンライン回線が4回線になります。それに伴い、5月7日以降の家庭学習支援について、次のように行います。
(1)学習プランはこちら。(e-Learningシステムからもダウンロードできます)。
5月7日(木)以降の学習プランを、追加します。
① 1学年
② 2学年(文系)(理系)
③ 3学年(文系)(理系)
※学習プランに沿って、効果的に学習をすすめていきましょう。
※随時更新します(更新の連絡は「すぐメール」で行います。)
(2)5月12日(火)以降のモデル学習時間割はこちら。
(5月7日,8日,11日は、これまでのモデル学習時間割を利用して下さい。)
① 1学年
② 2学年(文系)(理系)
③ 3学年(文系)(理系)
※モデル学習時間割に沿って、計画的に学習をすすめていきましょう。
※色付きのコマはオンライン学習支援講座と対応しています。
(3)5月11~29日のオンライン学習支援講座の時間割はこちら。
回線①(1年生中心)〔5月11日(月)は回線①のみで行います。〕
回線②(2年生中心)
回線③(3年生文系中心)
回線④(3年生理系中心)
※他の回線を使用する講座もあります(モデル時間割に書いてあります。)
※新しい回線の「URL」や「ミーティング番号」は、5月11日(月)に「すぐメール」でお知らせします。
(4)教材配信はe-Learningシステムから。
【困ったことがあった場合や万が一の時のために】
次の4点を確認してください。
(1) 地震など自然災害発生時の避難場所や、緊急連絡の方法などを家庭で話し合っておきましょう。
(2) 学校に相談しづらい時は、以下の窓口に相談しましょう。学校に相談しづらい時は、以下の窓口に相談しましょう。
【いじめ・不登校・虐待・学習・進路・人権に関すること等についての相談電話】
◇子供SOS24 : 0120-0-78310 (夜間・休日・祝日全24時間体制)
◇教育相談ほほえみダイヤル : 0120-745-070 月~金 8:30~17:15(祝日は除く)
(3) 何か困ったこと、相談したいことがあれば学校に連絡しましょう。
電話番号: 0577-32-0075
(4) 事件・事故等があった場合は、『110番』または地区少年サポートセンター(最寄りの警察署の生活安全課につながります)に連絡しましょう。
電話番号:0120-783-802(フリーダイヤル)
オンライン授業開始時の注意について
オンライン授業開始時には、コールイン・コールバックによる接続をしないよう、気をつけてください。
○コールイン・コールバックについて
Webex Meetingsのコールイン・コールバック機能は、動画はインターネット、音声は国際電話通信を使い通話を行う機能であり、携帯電話から通信を行うと国際ローミングにともなう通話料が別途請求されることになります。絶対に「コールイン」「コールバック」はタップしないでください。「インターネット通話」による接続にしてください。
○確認方法(こちらを参考にしてください)
赤い矢印部分を左から順にタップすると、音声通話の状態を確認できます。「インターネット通話」になっていることを確認してください。自分のオンライン授業開始時に、常に確認してください。一度「コールイン」「コールバック」機能を使ったことがあると、自動接続される場合があるようです。







