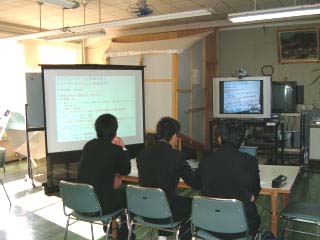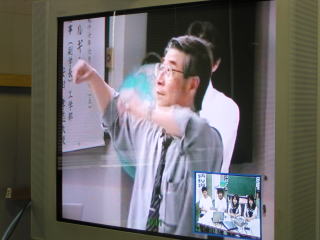

SSH土曜講座ネットレクチャーとは
↓
岐山高校で行なっている先端科学講座授業を、
テレビ会議で中継して本校生徒の希望者対象に実施する講座です。
平成17年度第1回SSH土曜講座・「気象とエネルギー」
6月11日(土) 9時00分〜12時00分 希望者を募って実施
講師 安田 孝志 先生(岐阜大学大学院工学研究科環境エネルギーシステム専攻・教授、副学長)
事前に岐山高校と恵那高校のピンポイント天気予報を安田先生の研究室HPに掲載して頂き、また、1時間毎の予報をメールで送っていただき、予報と実際の天気を比較してこの授業に臨んだ。
<講義の概要>
自然現象の支配法則を知り,それを数学的に表現することによって様々なことが統一的に理解できるようになるだけでなく,コンピュータの利用によって様々な応用が開けることを身近な気象を例に学ぶ。
1 気象の異常を感じる
・東海豪雨災害(2000年)・2004年台風災害・ヒートアイランド・温暖化
2 電気を生む気象
・水力発電・風力発電・太陽光発電
3 気象を科学する
・気象の仕組み−水が鍵−・数学で表す気象・コンピュータが描く気象
・台風の再現
4 気象を工学する
・風力発電の適地はどこ?・私の家の発電量は?・気候に適した土地の利用
5 岐阜大学発の天気予報の紹介
日本の大学では初めて,気象モデルによる2km解像度予報は日本で最初
<感想>
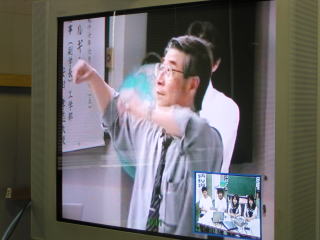

平成17年度第2回SSH土曜講座・「金属の加工 − 塑性加工」
7月2日(土)9時00分〜12時00分 希望者を募って実施
講師 佐藤 丈士 先生 (岐阜県製品技術研究所 専門研究員)
<講義の概要>
金属を指定した形状に変えることを加工といいます。私たちの身の回りには、金属でできている物、つまり金属を加工した物がたくさんあります。これらはどのような方法で作るのでしょう。金属を加工する方法はいろいろあります。今回は、聞き慣れない言葉であるとは思いますが、塑性加工法を取り上げます。そして塑性とは何かから始まって、具体的な金属製品と絡めながら塑性加工に利用する金属の種類、個々の塑性加工法を紹介します。
<感想>


平成17年度第3回SSH土曜講座・「革新的新素材ーカーボンマイクロコイルーその未来像」
11月12日(土)9時00分〜12時00分 希望者を募って実施
講師 元島 栖二 先生 (岐阜大学工学部応用化学科教授)
<講義の概要>
大宇宙や大自然には渦巻きがいっぱい、私たちの身体も“うずまき・らせん構造
「ミクロの世界の渦巻き/らせん構造が輝かしい未来をつくる」
渦巻き銀河、太陽や地球の動き、テレビ・ラジオ・携帯電話・電子レンジなどに使われる電磁波、つる性植物性や巻貝、あるいは私たち生物を構成しているDNA(遺伝子)やたんぱく質など、多くのものが渦巻き・らせん構造をしている。自然の創造主(神)は様々な渦巻き・らせん構造をつくりあげた。しかし人類はこれまで、科学技術が高度に進歩した20世紀にも、このような構造を持つ物質(材料)を作ることが出来なかった。21世紀に入り、我々はようやく渦巻き・らせん構造をした革新的新材“カーボンマイクロコイル(CMC)”を作ることに成功した。人類は、ようやく神の領域に踏み込むことができ、輝かしい未来が開けようとしている。科学技術の高度の進歩をもたらした多くの偉大な発明・発見は、“偶然”見出されたものが多い。誰にでも偉大な発明・発見のチャンスはある。
この講演では、自然・生物のうずまき・らせん構造を考えながら、21世紀の革新的新素材であるカーボンマイクロコイルの発明・発見の物語、その幅広い応用と未来像についてお話し、これからの科学技術の進むべき道を考える。
<感想>